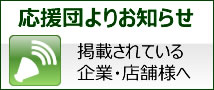南三陸情報誌 vol.1 – まちの記憶 心に焼きつけて
まちの記憶 心に焼きつけて
浜の漁師たちは声をかけあい
競い合いながら、漁を営んできた。
知恵を出し合いながら、
カキ、ホヤ、ワカメを育ててきた。
凍てつく冬
浜の家々をまわる
子どもたちの歌が
風にのって聞こえてくる。
家々の神棚には
縁起物が切り透かされた
白い紙が飾られる。
白一色の清楚な美しさが
里海の里によく似合う。
夏
船上の大きな絵灯籠に火が灯り
夜の海は幻想の世界になる。
男たちが点けた灯火が
かつて入り船を迎えてきた
川面を焦がす。
私たちは唄い、舞う。
大漁と五穀豊穣を祈り、祝う。
明治、昭和に三度襲った
津波の被害を乗り越え
流されても流されても
一軒一軒、それぞれの営みを
再生してきた。
その度に
みんなで知恵と力を出し合った。
決してあきらめることなく
みんなでまちを再生し
笑顔を絶やさなかった。
その背中を
子どもたちは見て来た。
山には
米も、豆も、りんごもなる。
収穫を前に
山間に打ち囃子が響き渡る。
色鮮やかな装束や花御輿に
おとなも子どもも胸躍らせる。
漁師は山に木を植え、海を耕す。
鮭ははるばる長い旅の末に
決して迷うことなく
南三陸の湾に戻ってくる。
ダンゴウオや
グラントスカルピン、
新種のヒトデも生きている海。
人も緑も魚も、
一緒に生きていると
実感できる里海の町。
それが南三陸だ。
今、胸の中に
生き生きとよみがえる町の記憶。
やがて薄れてしまうのでは
ないだろうか。
そんなおそれが脳裏をよぎる。
私たちは、
大自然のおそろしさと
ありがたさを知っている。
だから、生かされている身の
謙虚さを忘れることはない。
先祖代々、そうしてきたように
どんな時にもあきらめることなく
明日を信じ続けよう。
自然と共に生きていこう。
手に手を取り合って
力を合わせれば
どんなことでも実現できると
信じよう。
今を懸命に生きれば生きるほど
記憶は美しい輝きを増すものだ。
豊かな山がゆっくりと
海の恵みを育むように
幸せなみんなの町は
きっといつか再生する。
どんな試練があったとしても
海のように大きな心を持とう。
この町を訪れる人たちとつながって
新しい力を取り込もう。
潮は満ち、潮は引き
今日も海を見ながら
わたしたちはこの町で生きている。
里海に生きる誇りを
しっかりと心に抱きながら。
若返った海を未来へ
村岡 賢一さん
漁師
村岡賢一さんは、集落の中心となって、水産業の振興や南三陸町を代表する伝統芸能のひとつである行山流水戸辺鹿子躍の保存に力を尽くしてきた。村岡さんが住む戸倉・水戸辺地区では、隣りの在郷地区と契約講の絆で結ばれた住民たちが、昔から海の仕事、森林や鮭が遡上してくる川の管理、運動会など、何でも一緒に力を合わせて来た。自然に生かされていることを知り尽くした先人たちが、生きるために協働する集落を守り、継承してきた。
震災後、団結はますます固くなった。何もかも失われ、13隻あった船が3隻になった集落で、2つの地区の人たちはともに復旧活動に汗を流した。避難所で子どもたちと共に練習を再開し、鹿子躍を全国10数ヵ所で披露した。秋の終わりからは、ワカメの刈り取りやカキの養殖準備も行っている。
津波で海が若返った、と村岡さんは語る。カキやワカメの生育状況の速さでそれが実感できる。自然がすべてを育ててくれる。人間がこの海で漁や養殖を営むことは両刃の剣だ。よみがえった海を人間が大切にすれば、海は永遠に恵みをもたらしてくれるだろう。自然のサイクルを止めないこと。それが南三陸の海で生きる人間にとって一番大切なことだと村岡さんは考えている。
「子どもたちに豊かな自然を残したい。その恵みこそ未来を潤す、かけがえのない財産だ。」
村岡さんは、今日も水戸辺の浜から海に出る。何万回この海に出ても同じ思いが胸をよぎる。
「漁師の仕事はきびしい。出船の時は希望と不安がいりまじる。そして、陸に向かって帰るときは、心が安堵で満たされる。」
太古の昔から変わらぬ自然と人の関係を、このまま変わらずに伝えることこそ、何より大切なことなのかもしれない。そう村岡さんは思う。
多くの人を呼び込む町へ
三浦 洋昭さん
株式会社マルセン食品 代表取締役
株式会社マルセン食品の三浦洋昭社長は、志津川地区の「おさかな通り」にオープンしたての店を大津波で失った。震災前、鮮魚はもちろん、水産加工品や惣菜、地場の農産品も扱っていた新しい店は地元の人たちの支持を得て、徐々に売上を伸ばしていた。
3月11日、三浦さんは一瞬のちに、家、店、工場、何もかもを失った。残ったのは借金だけ。目の前には、原始の昔はこうだったのだろうかと思えるような風景が広がり、海が不思議なほど近くに見えた。
従業員を断腸の思いで解雇したあと、福興市、会社の再建など、すべてを同時並行で進めて行かなくてはならなかった。おさかな通りの仲間たちも、みんな同じ境遇だった。これまでも南三陸をPRするために、連携してがんばって来た仲間たち。互いに支え合い、力を合わせた。
7月には、移動販売車で食品や日用品を仮設住宅に出張販売する仕事を始めた。海辺にかろうじて残された工場の建物をなんとか使えるように手を入れ、備品を購入し、12月に工場をスタートさせた。志津川地区の福興名店街で販売す
る鮮魚と商品で、なんとか経営を軌道に乗せたいと考えている。地元に愛される店、そして、遠くからもお客様が来てくれる店が、三浦さんの目標だ。
多くの人たちが来てくれる町にしなければ、商品も売れないし、未来も開けないと三浦さんは言う。
訪れる人を増やすためには、この美しい海の景観を絶対に守らなければならない。水産業、農業が連携する豊かな里海の恵みと景観こそが、この町の経済を支える産業に結びつくと三浦さんは考えるからだ。先祖代々継承されてきたライフスタイルを未来に伝えることこそ、多くのビジターにとって魅力的な町の底力になる。次代に生き残るためのヒントは、南三陸のこの風景、生活にある。
子どもたちにとって、今回の震災は忘れられない体験だっただろう。
「きびしい環境の中で生き残るための術を、子どもたちは身をもって学んだ。彼らが得た自然の中で生きる知恵を、都会の人たちや子どもたちに学んでもらえるようなしくみが作れれば、将来の南三陸に人々を呼び込む力になるだろう。 」と三浦さんは言う。
きびしい現実の先にある遠い未来を見据えていきたいと、三浦さんは笑顔で語ってくれた。
ひとつに力合わせて
及川吉則さん
株式会社マルアラ 代表取締役
水産加工業を営む及川吉則さんは、5つの水産加工場のうち4つを失った。加工業になくてはならないものは、なんといってもいい材料だ。工場を再建するためには、まず始めに生産者が復興しなければならない。そう考えた及川さんは何よりも先に、浜をまわって失意の底にあった漁師たちに声をかけ続けた。「隣りの浜ではワカメ始めたらしいぞ。」時には、『うそも方便』。漁師たちをたきつけた。
漁師たちは、沖に流されたメカブで養殖を再開。ホタテやカキのタネを入手し、漁も始めた。例年の倍の速さで育っていると感じるくらいに、海は最高の状態だ。「次は、浜の人たちが水揚げした商品の販路を維持しなければ。」及川さんの表情が引き締まった。
及川さんはこれまで小売りは行っていなかったが、震災後初めて歌津地区伊里前の福幸商店街に店を出した。これまでには、出会わなかった人たちと出会い、作っていなかった商品を作る。思いもかけない新しい体験が続く。毎日が発見である。「これはチャンスなのかもしれない。」及川さんは前向きにとらえている。
海の最高の状態を保ち、水産物の質を高めるためには、密殖を防ぐために、南三陸全域の水産関係者が力を合わせるなければならない。今がその時だ、と及川さんは語気を強める。みんなで心ひとつに南三陸の海を日本一にしたい。
町並みが消えた伊里前の店からは、海が見える。海辺の店に、町の人たちが集まってくる。そんな風景がいとおしいと及川さんは感じている。豊かな海とその海が見える環境、そして、地域の人同士の心のつながりを未来に伝えていきたいと心から思う。
生きる楽しさを 見つけること 笑顔で生きること
小島 孝尋さん
大雄寺住職/あさひ幼稚園園長
大雄寺は、世界遺産平泉を隆盛に導いた3代目藤原秀衡の子息 高衡によって開かれた歴史の古い寺である。本堂内には、間引きを思いとどまらせるための古い絵図や地獄絵図、寛永時代の制札、過去帳など貴重なものが多く残されている。また、色鮮やかな花鳥風月の天井画は、時を経ても色あせることなく、極楽浄土の安らかな世界に観る者をいざなう。地獄絵図の隣りに安置されている結縁観音の穏やかな表情に向き合うと、心が静まっていく。傷ついた心を癒してくれるかのようだ。
住職の小島孝尋さんは、「残された者は、生かされたことに感謝し、犠牲になった人たちを供養する務めがある」と、町の人たちを励ましている。たとえ町から遠く離れたとしても、生まれ育った町のこと、生きて来た舞台である町の風景、まわりの人たちとのおつきあいとご縁、ふるさとの海の恵み、山や田畑の恵みを、決して忘れないで生きてほしいと語る。
大雄寺の参道には、古刹の風格を物語る見事な80本もの杉並木があった。その大木の60本が大津波で流失した。残った杉を、塩害のため伐採せざるをえなくなった。小島さんはこの杉を使って、自ら園長を務める幼稚園の園舎を再建することにした。これまで何百年もの間、雨風から寺を守ってくれた杉たち。その木が今度は、南三陸の未来を担う子どもたちを守ることになる。そう思うと、小島さんの胸には「ありがとう」という感謝と共に、万感の思いがこみ上げてくる。
南三陸の子どもたちは、震災直後からどんなにつらい状況になっても、いつも楽しいこと、おもしろいことを見つけ、友だちと笑顔でふれあっていた。これこそ人間の持つ底力である。子どもたちに教えてもらうことは多々ある。小島さんは今日も、元気いっぱいの子どもたちをやさしく見守っている。
記憶という宝物を千年後の人たちへ伝えたい
工藤 真弓さん
上山八幡宮 禰宜
南三陸の家々の神棚には美しい白い紙が飾られている。縁起物が切り透かされた「きりこ」である。「鯛飾り」と呼ばれる心楽しくなるような飾りもあり、清楚な華やかさを醸し出している。神社の宮司が、氏子のために作るもので、神社毎にデザインも異なる。
上山八幡宮の工藤祐允さん、庄悦さん父子は、かろうじて残った神社の社務所で、再び「きりこ」を作り始めた。「きりこ」は、町の人たちが共有できる、心安らぐ祈りの形だ。
工藤宮司の実の娘の真弓さんは、集団避難先で津波の体験や避難所での生活の機微を五行歌に詠んだ。真弓さんの五行歌を通して、共に暮らす人たちは思いを共有し、悲惨な体験を客観視することができた。現在暮らしている登米市南方の仮設住宅でも、町を離れて暮らす人たちが自然に集まれるような場を作ったり、「ぼくのふるさと」という紙芝居を自ら創作して、津波で町並みが失われても、心のふるさとは決して失われないことを伝え始めている。
何もかも失ってしまったと町のおとなたちは嘆く。孫と遊ぶ川もどんぐりの木もなくなってしまったと。そうお年寄りが話すのを聞いて、真弓さんの5歳の息子が、「どんぐり、なくなってないのに・・・。」と憤慨した。子どもの心の中には、どんぐりがたわわに実をつけているのだ。そう真弓さんは思った。
心の中には記憶という宝物が生きている。町の人たちの心の中に生きている記憶と大津波のおそろしさを伝え続けることが、千年後の子孫を救うことにつながると真弓さんは考えている。「今こそ、目線を遠くに置くことが大切。自分のできることは限られているけれど、今ここにいるはずだった、この町を愛していた多くの人たちの思いを胸に、祈りながら生きていきたい。決してすべてを失ったわけではない。豊かさとは心の内側にたまっていくものです。その内側に人は支えられるものだと思います。」真弓さんの目は、きらきらと輝いていた。
みんなのために生きていく
菅原 長弥さん
民宿 下道荘 主人
青い海に白い船が浮かぶ袖浜漁港に面した民宿街に、菅原長弥さん一家が家族で営む民宿下道荘はあった。息子の由輝さんとともに早朝から海に出て収穫した新鮮な魚介類を、由輝さん自らが腕をふるって調理して来た。新鮮な旬の料理が豪華にならぶお膳に歓声が湧き、常連客が笑顔でやって来た。
3月11日袖浜地区の民宿は、下道荘をはじめ8軒すべてが津波に飲み込まれた。32年間、妻と共に積み上げて来たすべてが無になったと、菅原さんは絶望した。
3月末に再建を決意したものの、地域の人たちがつらい状況の中、我が家だけが再開していいのか、何もなくなったこの町にやってくる人がいるのか、迷い悩んだ。眠れぬ日々が続いた。
だが、この町を再建するためには、人を呼び込まなければならない。そのためには、だれかが再開しなければならない。やるならば、被災地であることに甘えずに、変わらないおもてなしをしたい。菅原さんは心を奮い立たせた。
土地を交換してくれた方、瓦礫の片付けや竹藪刈りを手伝ってくれたボランティアさんたち、大工の棟梁、たくさんの人たちの力と励ましが、新生道荘の再スタートに結実した。2月17日にオープンした下道荘の壁面には、「絆∞感謝」という大きな看板が掲げられている。みんなのおかげでここにあることを表したい。菅原さんのそんな強い思いがそこに込められている。
新しい下道荘は、以前よりさらに高い場所に建てられ、すべての部屋から海が見渡せる。自家製の心づくしの食材で、南三陸ならではのおもてなしをしたい。それが南三陸の心意気。今こそ、それを見せる時だ。自分たち一家のがんばりが、町の人たちを励ますことになればうれしい。
今回の震災で菅原さんは、支援してくれた多くの人たちに、自分にないものを教わったと感じている。
「今までは自分のために生きて来た。でもこれからは、みんなのために生きよう。そんなふうに、この頃思うんですよ。」
タグ: 南三陸